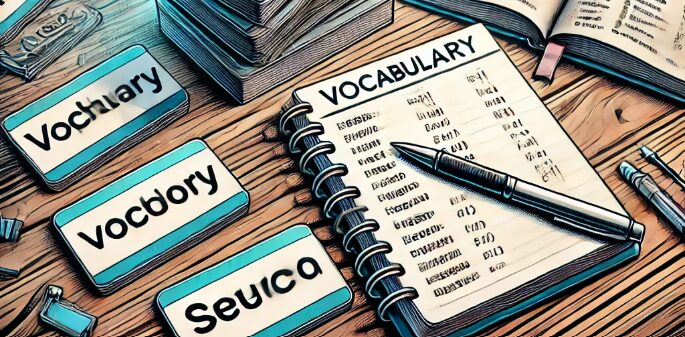「英単語を覚えたいけど、なかなか覚えられない」
「単語帳を買ったけど、途中で挫折してしまった」
そんな経験はありませんか?
実は、私もまったく同じ悩みを抱えていました。
しかし、私は半年間で6,000語を習得することに成功しました。
また、単語力のゴリ押しでTOEICで830点を取得することに成功しました。
その時の経験談は下記に詳細記載しています。
TOEIC700点から800点へ!私が実際にやって効果のあった勉強法を紹介
そのときに感じたこと、実践した具体的な方法、そして心が折れずに継続するための考え方をこの記事にまとめました。
ぜひ参考にしていただければ嬉しいです。
そもそも英単語をたくさん覚える必要があるのか?
そもそも本当にそんなに多くの英単語を覚える必要があるのでしょうか?
おそらく、簡単な英会話をしたいだけなら中学レベルの語彙力で十分です。
簡単な単語を組み合わせるだけでも、言いたいことは伝わります。 相手も同じように簡単な単語で話してくれるので、特に問題はないでしょう。
しかし、ネイティブ向けの新聞、ニュース記事、ドラマ、SNS、洋書などを読もうとすると話は変わってきます。
語彙力が6,000語程度あれば受験には対応できるかもしれませんが、 これらの情報媒体を読むにはまだまだ力不足です。
文法をどれだけ学んでも、語彙力の壁には必ずぶつかります。 逆に、文法知識が曖昧でも単語さえわかればある程度意味を推測できることがあります。
つまり、文法力では単語力を補えませんが、単語力で文法力をある程度補えるのです。 英語を本格的に学ぶなら、語彙力の強化は避けて通れない道です。
よく目にする甘い言葉があります:
文章から推測すればいい
コアの意味を一つ覚えておけば暗記する必要はない
果たして本当にそうなのでしょうか?
私も当初はこれらの言葉を信じていましたが、今はそうは思いません。 以下に、それぞれに対する私の意見を述べます。
「文章から推測すればいい」
確かに「〜or〜」のように、対比表現などでは 「これは反対の意味だろうな」と推測できるケースもあります。
しかし、いきなり“pangolin”のような単語が出てきたらどうでしょうか? 私はまったく推測できませんでした。
特に固有名詞や専門用語は推測が非常に難しいです。
常に前後の文脈があるとは限らないため、判断に困る場面も多々あります。
実際に洋書を読んでいたり英会話をしていたりすると、文脈から推測できない状況によく出会いました。
私の感覚では、TOEICの長文問題でも 単語の意味があいまいだと内容が頭に残らないと感じます。
長文を読み終えてから問題を読んだときに、内容を忘れていることもしばしば。
TOEICに限らず、資格試験の読解問題攻略には語彙力が非常に重要だと思っています。
「コアの意味を一つ覚えればいい」
確かに「コアの意味」を理解することは、英単語を覚える上で非常に有効です。
しかし、「コアさえ覚えれば他は覚えなくてもいい」という考え方は不完全です。 基本的な意味や使い方を幅広く押さえたうえで、忘れたときにコアの意味を手がかりに思い出す。 このアプローチが、最も実用的だと私は考えています。
また、コアの意味だけを頼りに毎回連想ゲームのように意味を推測していては、 リスニングでは確実に置いていかれます。
語彙が豊富であればあるほど、英文を読むスピードは確実に上がります。 特に簡単な文章であれば、文法を一つひとつ分析しなくても、 目に入った単語の流れから自然と意味がつかめるようになります。
その結果、英語の読解スピードが大きく向上したことを実感しています。
英単語を覚えることのメリット
語彙制限なしの洋書が読めるようになる
Penguin Readersなど、英語学習者向けにレベルを抑えた読み物がたくさん出版されています。
中学レベルの語彙力でも読めるような本が多く、初心者にはとてもありがたい存在です。
しかし、それが本当にあなたが「読みたい本」でしょうか?
読みたい本、知りたいことが書かれた本があるのに、
なぜ語彙力の壁に遮られなければならないのでしょうか?
語彙力が足りないという理由だけで、興味のある情報にアクセスできないのは非常にもったいないことです。
語彙力という壁を壊すことができれば、読みたかった本の世界、自分の関心のある分野へと自由に飛び込むことができます。
語彙の制限に縛られずに、英語の世界にもっと積極的に飛び込んでいきましょう。
また、語彙力をつけて自分の好きな本やウェブサイトをたくさん読む習慣ができると、自然と英語を読む速度も上がり、文の意味を素早く把握できるようになります。
さらに、その効果はリスニング力にも波及します。
読解のスピードが上がることで、英語を聞いて理解するスピードも上がり、
耳が自然と英語のテンポに慣れていくのです。
結果として、英語を「読む」「聞く」両面での力が飛躍的に高まり、英語学習がより楽しく、実用的なものへと変わっていきます。
語彙力の強化は、自分の世界を広げるための最強のツールになるのです。
英語が学ぶものではなく使うものになる
語彙力が増えると、英語は「勉強するもの」から「実際に使う道具」へと変わっていきます。
新聞の記事、X(旧Twitter)の投稿、さまざまなウェブサイト、
動画の字幕やコメント欄など、実生活の中で英語を使う場面は想像以上に多いのです。
語彙力を身につけることで、こうした情報源にも自信を持ってアクセスできるようになり、
世界中の情報を手に入れる手段が格段に広がります。
インターネット上に存在する英語の情報量は、日本語の約8倍とも言われています。
その中には、一次情報、最新ニュース、研究論文、製品レビュー、専門的なチュートリアルなど、質の高い情報が多く含まれています。
英語のWikipediaは日本語版よりも項目数が多く、詳細な記述も豊富ですし、マニアックな話題にも触れられています。
また、プログラミングやデザイン、ビジネス、マーケティングなどの分野では、英語のサイトの方が情報が早く、深く、分かりやすく解説されていることに気づくこともあるでしょう。
さらに、世界中のオンライン講座(MOOCs)やYouTubeチャンネルの多くは英語で発信されています。
語彙力が十分であれば、それらのコンテンツを字幕なしでも楽しみ、学びを深めることが可能になります。
このように、英語が「学ぶための対象」から「世界とつながるための実用的なツール」へと変化していくのを実感できるのは、語彙力がついてこそです。
翻訳サイトを使えないシチュエーションに対応出来る。
私は製造現場で働いていますが、紙の説明書、機密上翻訳サイトが使えない文書、
オフラインの設備の操作手順など、翻訳サイトが使えないシチュエーションは実際に数多く存在します。
特に、製品の仕様書やトラブル対応マニュアルなどは内容が専門的かつ機密性が高いため、
外部の翻訳サービスを使うことが禁止されていることも少なくありません。
こうした現場では、自分自身で英語を理解する力が必要不可欠になります。
また、オフラインで作業しているときや、通信環境が不安定な場所では、
そもそも翻訳サイトにアクセスすることすらできないケースもあります。
突然出てきたエラーメッセージや表示パネルの英語が読めなければ、
作業がストップしてしまう危険もあるのです。
よく「翻訳ツールがあるから英語は不要」といった声も耳にしますが、
現実にはその翻訳ツールが使えない状況もあるということを意識しておく必要があります。
さらに、毎回調べる手間を考えると、いちいち翻訳サイトに投げるのは面倒で非効率ですし、
翻訳の精度も完璧ではないため誤訳のリスクもあります。
だからこそ、自分の語彙力を高めておくことで、どんな状況にも柔軟に対応できる力が身につくのです。
試験など単語力ゴリ押しで高得点が狙える
語彙力を鍛えることで、試験におけるパフォーマンスは大きく向上します。
分からない単語が減れば減るほど、文章の意味を素早くかつ正確に読み取れるようになり、読解スピードと精度の両方が上がります。
私の経験では、語彙力を上げれば上げるほどTOEICのスコアも着実に上がっていきました。
特に英検では、語彙力そのものを問うパートが存在しており、
しっかりと単語を覚えていれば、そこで一気に得点を稼ぐことができます。
語彙問題が得意になるだけで、全体の得点が底上げされ、合格への大きな後押しになります。
TOEICの場合、「難しい単語は出題に直接関係ないことが多い」と言われることがありますが、実際には語彙力の有無で読みやすさや自信が大きく変わります。
私自身、選択肢を選ぶときに分からなかった単語がちらつくことで、
確信を持てずに迷ってしまうことが何度もありました。
しかし、語彙力をしっかりと鍛えることでその迷いはなくなり、自信を持って選択できるようになりました。
さらに、リーディングセクションでは、語彙が豊富なことで速く読めるようになり、
時間内にすべての設問に取り組めるようにもなりました。
リスニングにおいても、意味を即座に理解できるようになることで、選択肢を聞き逃すリスクが減ります。
このように、語彙力の底上げは試験全体のパフォーマンスを高める非常に効果的な手段であり、スコアアップには欠かせない要素だと実感しています。
習得語彙数ごとのレベル
あくまで主観ですが、各習得語彙数ごとに私が感じた状態を紹介します。語彙力の変化によって、英語の見え方・使い方がどう変わっていくかの参考になれば嬉しいです。
6000語レベル
英会話を目的とする場合、おそらくこのあたりの語彙力で十分です。日常会話に必要な単語はほぼカバーできますし、TOEICでも大体の問題に対応できる単語力が身につきます。
ただし、洋書やネイティブ向けのニュース、SNSなど、いわゆる“野生の英語”には太刀打ちできません。知らない単語が頻繁に出てきて、意味が分からずにストレスが溜まりやすい段階です。
8000語レベル
TOEICでのスコアに直結する単語は、ほぼすべて理解できるようになります。リーディングセクションでのスピードや正確性もこのあたりから安定してきます。
ただし、一般的な洋書を読むにはまだまだ語彙が足りず、頻繁に辞書を引くことになります。読みたい本に挑戦しても途中で断念してしまうケースも多く、実用面での壁を強く感じるレベルです。
10000語レベル
TOEICで出題される単語はもちろん、解答には直接関係しない表現も理解できるようになります。語彙が豊かになることで選択肢を見て直感的に判断できるようになり、自信を持って答えられるようになります。
洋書も本によってはなんとか読めるレベルです。理解に時間がかかることもありますが、辞書を使えば内容を追うことができるため、英語読書の楽しさを少しずつ実感できるようになります。
12000語レベル
TOEICで知らない単語に出会う確率はほとんどなくなり、語彙問題も難なく解けるようになります。洋書も辞書を引く頻度が大幅に減り、読み進めるのがスムーズになってきます。
語彙力があることで読解スピードも上がり、読書自体が楽しくなります。さらに、リスニングやライティングでも語彙が豊かであることが大きな武器になり、表現の幅も広がります。
6000語までは『DUO』と『金のフレーズ』を主に使って単語を覚えていました。同時に文法の学習もしていたので、どちらが効いたのか正直わからないところもあります。
ただ、どのレベルでも一つだけ言えることがあります。
1000語覚えるたびに、見える景色がガラッと変わります。
英語でネット検索するのが当たり前になったり、SNSやニュースの内容が理解できたり、辞書を引く回数が減るたびに成長を実感できます。
当然、TOEICの正答率もどんどん上がっていきます。
しかし、10000語を超えたあたりからは、単語帳で覚えた単語と実際の文章で出会う機会が減ってきて、モチベーション維持が難しくなることもあります。
さらに、これまでに覚えた単語と似た綴りの単語を整理して覚える必要が出てきて、記憶の整理も重要になります。根気よく、効率的に学習を続ける姿勢が求められるステージです。
継続のコツ・意識すること
一度では絶対に覚えられない
一度では絶対に覚えられません。忘れては思い出してを繰り返して、ようやく脳に定着します。これは英単語に限らず、何かを覚えるという行為すべてに共通することです。
「覚えたつもりだったのに、また忘れてしまった」と感じたとき、その繰り返しこそが記憶を強固にするプロセスの一部なのです。なので、一度で覚えられないからといって落ち込まず、当たり前のこととして受け入れましょう。
復習の頻度やタイミングを工夫することで、効率よく定着させることも可能です。忘却曲線を意識した学習スケジュールを取り入れて、無理なく記憶に残していきましょう。
ズルしていると思う
英語学習でも「楽したい」「ズルしたい」と思うこと、ありますよね?私もそうです。単語をコツコツ覚えるのは地味で退屈な作業に思えることもあります。
でも実は、単語を効率よく覚えるという行為は「ズル」ではなく、賢い戦略だと考えています。日本語を習得する際には単語帳など使ってこなかったかもしれませんが、それは日常生活の中で何年もかけて自然に身につけてきたからです。
英語は後から学ぶ言語です。限られた時間の中で効率よく吸収するには、意図的なインプットが必要です。
単語学習は、膨大な時間を短縮するための強力な手段であり、むしろ努力の証。登山で例えるなら、遠回りの登山道ではなく、体力勝負で急斜面を登るようなものです。しんどいけど、たどり着くスピードは早い。
「ズル」だと感じるくらいのスピードで、どんどん覚えていきましょう。それが、語彙力を一気に引き上げる近道です。
眺めるだけで満足する
単語帳を開いて眺めているだけで、つい「勉強した気」になることってありませんか?
でも、覚えようとしても覚えられなかったとき、自己嫌悪に陥る必要はまったくありません。
私は「記憶に残ればラッキー」という感覚で、まずは気軽に単語帳を眺めるようにしています。
毎回完璧に覚える必要はありません。何度も繰り返す中で、自然と記憶に染みついていきます。
こうした軽い姿勢のほうが、精神的な負担が少なく、結果として継続しやすくなるのです。
「一語一語しっかり覚えなければ」というプレッシャーを手放し、
「目に触れ続けていれば自然に覚えられる」くらいの気持ちで続けていきましょう。
英単語を覚えている理由をはっきりさせる。
なぜ英単語を覚えたいのか?自分の中でその理由を明確にしておくことが、学習を継続するうえでとても重要です。
「TOEICのため」だけでは、正直モチベーションとしては弱いです。
例えば、「TOEICの長文でつまずくのは、いつも単語の意味がわからないことが原因だった」「洋書を読みたいのに、語彙が足りなくて読み進められない」など、具体的な悩みと結びついた理由があると、学習の意味が明確になります。
「語彙力さえあれば、もっと理解できるのに」という思いが強くなればなるほど、単語学習にも熱が入ります。
目標を「点数」ではなく、「できるようになりたいこと」「困っていることを解決したい」という目的に置き換えると、途中でブレずに学習を続けやすくなります。
覚えた単語の数を数値化してみる
英語学習は成果が見えにくいことが多いですが、語彙力は唯一「数字」で見える指標です。
「何語覚えたか」「前回の語彙診断からどれだけ増えたか」など、数値を通じて成長を実感することで、モチベーションが大きく向上します。
語彙診断サイトを活用したり、Ankiや単語帳の進捗を記録したりするのがオススメです。
また、SNSで記録をシェアしたり、仲間と進捗を比べ合ったりするのも、学習を楽しく続けるコツです。
一回やめてみて覚え直す苦痛を味わう
一度覚えた単語を全部忘れてしまったときのあの絶望感……私は一気に1000語覚えたあと、復習をサボってしまい、全て忘れてしまった苦い経験があります。
その後、もう一度同じ単語を覚え直す作業は、思った以上に時間と精神力がかかりました。
でもその経験から、復習の大切さと「忘れる前に触れる」ことの重要性を痛感しました。
今では、あの時の苦痛を思い出すことで、自然と復習を習慣化できています。忘れたことの悔しさが、継続の強い動機にもなるのです。
一生英語を勉強する覚悟で取り組む
英語学習は一時的なプロジェクトではなく、一生続くライフワークだと捉えると、気持ちがとても楽になります。
「この単語、今すぐ覚えなくてもいいかな?」と思うこともあるでしょう。 でも、出会った単語はどこかでまた再会する可能性があります。
「そのときに覚えていれば楽になる」と思えれば、今覚えておく意味が生まれます。
私は“daffodil”という単語を「こんなの覚えなくていい」と流していましたが、数日後にTOEIC公式問題集で再会したときの感動は忘れられません。
一生英語を学び続ける覚悟があれば、「今は必要なくても、いつか絶対使う日がくる」と信じて、前向きに単語学習を続けることができます。
具体的な覚え方
英単語を効率的かつ着実に覚えるために、私が実践してきた具体的な学習法を紹介します。忙しい社会人の方でも取り入れやすく、続けやすい方法なので、ぜひ自分のスタイルに合わせて試してみてください。
1.単語帳を区切る
単語帳を最初から最後まで一気に覚えようとすると、最初に学んだ内容を後で忘れてしまう可能性が高いです。
例えば「1日に10単語ずつ覚えていく」というような、少しずつ進める方法もありますが、復習のスパンが空きすぎると効率が下がってしまいます。
そのため、効率的に覚えるには、1回の学習時間で2周できる程度の量に区切るのがベストです。
私の場合は通勤電車の片道が約1時間だったので、200〜300語程度を1セットとして繰り返し学習していました。一つの範囲を集中的に何度も見ることで、記憶の定着が飛躍的に高まります。
2.区切った範囲を何周も復習する+音源を聴き続ける
範囲を区切ったら、そこを何周も繰り返し復習します。10周程度では足りない場合もあります。目標の回数ではなく、「限られた時間内に何周できるか」を意識してください。
1週間ほど同じ範囲を毎日繰り返すと、自然とその単語たちは身についてきます。
そして、並行して音源を活用しましょう。視覚だけでなく、聴覚も使って覚えることで、記憶の定着率がぐんと上がります。発音も自然と身につくので、リスニング力や発話の精度にも効果的です。
私のおすすめは「ながら学習」です。通勤中、料理中、トイレ、寝る前など、イヤホンを常に耳に入れておくくらいの気持ちで音源を流し続けると、学習時間を自然に増やすことができます。
英語のみの音源が最初は辛いかもしれませんが、慣れてくると日本語の説明がない方がテンポよく学習できます。わからない単語があっても、聞き流しておくだけでも記憶には残ります。調べられないときは無理せず、「覚えておく努力」だけでも十分効果があります。
3.Ankiで復習する
単語を覚えた後に問題になるのは「忘れないようにすること」です。記憶は時間とともに薄れていきます。
そこでおすすめなのが、忘却曲線に基づいた復習アプリ「Anki」です。
Ankiは、あなたが忘れかけたタイミングで単語を出題してくれるので、復習の効率が非常に高く、短時間で最大限の成果を得ることができます。
ただし、最初からAnkiを使うのは少し難易度が高いです。知らない単語ばかりのときは、ページにまとめて載っている単語帳で先にざっくり覚えたほうが効率的。そのあとにAnkiで仕上げの復習を行うと効果的です。
単語登録の手間はありますが、自分でカードを作ることで記憶も深くなります。
4.Ankiで復習し続ける
Ankiは一度使い始めたら、できるだけ継続することが大切です。
私も現在6000語をAnkiで復習していますが、毎日コツコツやっていれば、1回の復習は数分で終わります。短い時間でも積み重ねれば大きな差になります。
英単語は一度覚えても必ず忘れます。だからこそ、継続的に復習する仕組みが不可欠なのです。
洋書、サイト、ニュースなど野生の英語に触れて再会する
6000語〜8000語を超えてくると、TOEICなどの試験ではあまり新しい単語に出会わなくなります。
ですが、リアルな英語の世界、つまり洋書・海外のニュースサイト・SNS・YouTubeのコメントなど“野生の英語”には、単語帳で見たことのある単語が頻繁に登場します。
「あっ!これ前に単語帳で見たやつだ!」という再会の喜びは、強烈な記憶に繋がります。忘れていた単語でも、この感情の動きによってしっかり定着します。
逆に、まったく初めて見る単語は印象に残りづらく、覚えにくいです。
この「知っている」から「使える」に変わるプロセスが、語彙力を本物に変えてくれるのです。
試験問題だけでなく、ぜひ自分の好きなジャンルや興味のある分野の英語に触れてみてください。そこには教科書では得られないリアルな英語の世界が広がっています。
語彙力は、あなたの世界を広げ、英語との距離をぐっと縮めてくれます。
どうしても覚えられない単語の暗記方法
何周も回してると自然と単語を覚えることが出来ますが、たまに何回見ても忘れる単語があります。覚えられない単語は下記方法で少し工夫して覚える必要があります。全ての単語に対して下記覚え方をしていると効率が悪いので、どうしても覚えられない単語のみに使用した方が効率がいいです。
例文ごと覚える
この覚え方のメリットは使い方も同時に学べる点と思い出しやすい点です。
例文で覚えていると一部分を変えるだけで文章が出来る(いわゆる英借文)のでスピーキングやライティングに応用が可能です。
例文を暗記していれば、仮に単語単体の意味が分からなくても、暗記済の文をヒントに意味を思い出すことが出来ます。
DUO等例文タイプの単語帳であればそのまま覚えれば良いのですが、単語だけ羅列しているタイプは自分で文章を作る必要があります。
自分が使いそうな文章でイメージを思い浮かべながら覚えるのが効果的です。どうしても思い浮かばない方はChatGPTに聞いて作ってもらいましょう。
語呂あわせ
語呂合わせはイメージと紐づいた語呂が出来れば望ましいです。
例えばですが、regret はピグレットが後悔している様子を思い出しながら「ピグレットがリグレット」と覚えました。
あと下ネタ系の語呂合わせは記憶に残るので最高です。ここでは言えないですが自信作が大量にあります、、笑
トイレ等にリストアップして貼る
私はどうしても覚えられない単語は書き出してトイレに貼って覚えてました。
純粋に見る回数が増えるので自然に覚えることが出来ます。
家族には何これと突っ込まれますが無視しましょう。
貼ってる跡が残らないようにマスキングテープで貼りましょう。
スマホの待ち受けにする。
覚えられない単語をリストアップしてスクショしその画面を待ち受けにしていました。スマホはかなり見る頻度が高いので待ち受けにした単語は確実に覚えることが出来ます。
絵で覚える
「覚えたい英単語 image 」で検索すればその英単語の画像が出てくるので、その画像で覚えちゃいましょう。
画像のスクショを撮っておいて、Ankiのアプリ上で画像を登録すれば回答後に登録した画像が表示されるようになります。
この機能是非活用しましょう!ちなみにAnki は画像だけではなく音も登録出来るので活用しても良いかもしれません。
Ankiの使い方はまた後日まとめようと思います。
最後に
いかがでしたでしょうか?
かなり長文になりましたが私が半年間単語学習をやり続けて気付いたことをまとめてみました。単語学習に終わりはないです。
覚えては忘れ、勉強を続けていると新しい単語に出会います。頑張りましょう!!